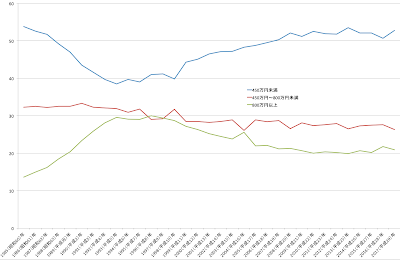インターネットが世界の人々の日常の中にしっかりと根付いた時代になった。多くの人がSNSのアカウントを持っている。SNSごとにアカウントを持ち、あるいは同一のSNSの中に複数のアカウントを持つこともありふれている。アカウントにはIDがありそのIDとアカウントはパスワードによって本人性が確保されている。アカウントの名前がIDとは別の場合もあるが、同じ時もある。どちらもアカウント名と呼ぼう。
私特殊なことかもしれないが、私は他にも、アマチュア無線局を運用していてそのコールサインもある。また、インターネットのドメインも運用していて(ex. washida.net)それもひとつのIDであり、名前である。
タレントや芸人などにはまたその世界で通用する名前を戸籍とは別に持っていることもあるだろうし、作家はペンネームを持っていて戸籍名と異なる場合がしばしばある。
これらの名前の全ては記号である。SNSのアカウント名が記号であるというのはわかりやすい。実際アルファベットとや数字の簡単な組み合わせになっているだろうからである。芸名もそれはアルファベットではないかもしれないが、記号である。ペンネームもまた記号である。
そして、さらには、われわれの戸籍名も記号である。戸籍名は、漢字やひらがななどを使っているので、記号らしくないかもしれないが、外国の場合アルファベットなので、そう考えるといくら漢字やひらがなで書かれていても、戸籍名記号であることは間違い無いだろう。
それでは、記号とは実体を短く象徴し代表するものである。記号のほかに実態が存在するのである。記号はアプリのアイコンのようにもおもえるが、それよりも確かな存在である。
人間は記号を背負って生きている。社会は全ての人間に少なくとも一つの記号を与える。戸籍名である。戸籍の名前の方は親などがつけるが、それは必ず役所に届けなければならず、そのときに社会に認知された名前、すなわち記号となる。戸籍名は社会によって強制的に与えられた記号なのである。
一方実体とは、その記号が代表している物理的存在、あるいは肉体的精神的存在である。
テレビドラマではよく記憶喪失者の話が出てくる。船で遭難して、記憶喪失になって知らない街にたどり着く。本人も周りもそのものの名前は知らない。したがって、記号を失った人間になってしまうのである。そのとき、その人と認識しうるものが全て実体である。名前を失った、記号を失った人間の実体である。
記憶喪失者の例で明らかなように、記号を失った人間は誰だかわからなくなってしまうのである。自分も自分がわからないし、周りもそれが誰だかわからなくなる。しかし、実体としての自分は記号を失って、記号に対する記憶を失ったとしても、認識可能である。
人は記号としての自己を認識することもできるし、実体としての自分を認識することもできるわけである。
人間以外の生物でも、一種の記号化に似た現象はある。コロニーで群れの中にいる自分の子供を匂いや鳴き声で区別できる動物は少なくない。しかしそれらは識別子としての記号であり、社会関係の中で機能する象徴としての記号ではない。人間の記号は社会関係の中のシンボルである。
その人間の社会関係は全て記号に結びつけられているのであって、当然実体としての肉体及び精神に結び付けられているのではない。
人間は記号を背負うことによって、曖昧さなく自己を意識させられる。しかし、もともと自己というのははっきりしない存在なのである。
あらためて「自分とは何か?」を問うて見る。一見、これほど馬鹿馬鹿しいと言わないように思える。自分とは何かと問われたとき、「自分は自分だ」とか、「自分は〇〇だ」と名前を答えることもあるかもしれない。自分は自分にとって自明の存在だと、誰もが思っている。思わないとまともに生きていけないと思える。しかし、自分にとって自分とはそれほど鮮明に理解しうるものだろうか。
たとえば、「自分のことはいくらよくわかっている」と言っても、病気になったとき、どのような病気であるかを即座に理解できない場合も多々ある。風邪くらいならば、わかるかもしれない。しかし大概は、医者から何の病気であるかを教えてもらうのである。自分の実態としての肉体をそれほど私たちは理解できないでいる。理解しないままに、何十年も私たちは肉体と精神を使用し続けるのである。まさにそれができるように肉体は作られている。自分を理解しなくても自分を維持できるようになっているのである。人間はロボットのように作られたものではない。途方もない時間をかけて、生命の進化を丹念に辿って、紆余曲折しながら人間は作られてきたし、その時速のためのソフトウエアを体内に、遺伝子の中に溜め込んできたのである。だから、自分というものをそう簡単に理解できるものではない。私たちが「自分のことはよくわかっている」というのは、「自分と他者、自分と環境の境界をよく理解し区別できる」という表現に変えると正確だ。あらゆる生命は、自己と他者あるいは環境の区別をする能力を持っている存在だからである。人は自分の内実を知っているというよりも境界を知っているのである。
粗に自分という存在の曖昧性は、生まれたばかりの自分は、単なる遺伝子の発現した物質でしかないということにも現れている。生まれる瞬間の自分を意識している人間はどこにもいない。生まれたとき、自分というのはそこに存在していなかったのである。その遺伝の発現した物質でしかない肉体は、栄養を保持し適切な環境を与えれば、いつか成人する。たとえ、そこに自分という明確な意識を持たなかったとしても、肉体的な実態は形成されるのである。だから、大人になって私たちが自分を意識しているときの肉体は、本来自分のものではなく、遺伝子が発現した物質が環境との相互関係の中で形成された物理的存在に過ぎないものである。
自分は、この遺伝の発現した物質が、他者や環境との境界を意識するようになったときに、その区別をしたこちら側の存在を自分を意識するようになっただけである。
すなわち、自分が自分を作り上げてきたというのは本質的に誤解であり、自分というものの中から、遺伝子の発現した物質という側面と、教育も含めた環境との相互関係が作り上げてきた側面を除くと、そこに自分という存在の余地はほとんどなくなってしまうのである。たとえば、受験勉強を必死でやって大学に合格したという場合、その努力をやったのは自分であり、大学に合格したのは自分の成果だというのは、一つの表現としては正しいが、その努力しようとした自分もまた、遺伝子の発現と環境との相互作用の中から生まれたものに過ぎないと言える。
われわれが自分と思っているものは、玉ねぎみたいなもので、遺伝子の発現と環境の作用だから自分と言われるものはないという形で、一つひとつ剥いていけば自分固有のものは何も無くなってしまうのである。
たとえそうであっても、自分は困るものではない。困るのは社会である。社会は、どうしても区別された個人でなければならず、社会の中で責任ある主体でなければならないのである。
わかりやすい例で言えば、犯罪がある。犯罪は、社会を維持するために誰もが守るべきルールを守らなかった罪である。とうぜん、それを犯した個人に責任がある。しかし、もしその個人が、自分は全て遺伝子が発現し、環境との作用で作られてきたもので、遺伝子と環境に責任があるから、犯罪は遺伝子と環境のせいだと言って、それが認められたらどうなるだろう。それはどう見ても正しい命題だが、それを認められば、この社会が成り立たなくなってしまう。
だから、個人は必ず責任ある主体でなければならず、それを確実にするために社会は人間に記号を付与し、個体を区別し、その記号を伴う人間に社会に対する責任を要求するのである。
記号としての自分は、社会が社会システムであるために発生するものである。この社会と社会システムの区分については別な論述に場所を譲らなければならない。
人は記号としての自分と実体としての自分に、二重化した自分を生きていかなければならない。記号としての自分だけが自分であると思い込んではならない。それは一面の自分でしかない。実態としての自分もまたかけがえない自分であり、自分の実体としての生が実現した理由を持つ自分であり、その自分を成立させた家族や環境と密接不可分の関係を持った自分であり、また自分の絶対的固有性を支えている基盤としての自分なのである。
インターネットに支配された現代は、人間を徹底的に記号化する時代である。くれぐれも、自己の記号化し多側面だけを自己と錯覚することがないようにしなければならない。